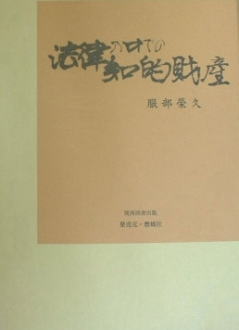 |
ISBN4-88978-029-7 |
服部 榮久著 |
A5判上製168頁
定価 (本体2,000円+税) |
|
|
| |
特許にかかわる法律知識 |
法律の中での知的財産 |
「人生七十古来稀」 ということで、私もとうとう稀な人間の仲間入りをすることになってしまった。
10年前に還暦を迎え、この世に生を受けてから暦が丁度一巡したということで、働く人生も停年で終わり、後は余生を楽しもうといったことが盛んに言われていた。
しかし私はそうは思わなかった。 暦が一巡したのであるから、一通りの人生経験を積んだことになり、これからが本当の勝負なのだと思った。
三段跳びに例えれば、今までの人生は、ホップステップに相当し、これからが本番のジャンプなのだ、というのが私の気持ちであった。
私は、停年とか余生とかいう言い方は好まない。 私の人生は、 キャラメルのおまけでもなければ、余り物でもない。
今までの経験を生かして最大の努力を続けて行きたいと思い、それを実行して来たつもりである。
そこでこの度、 「古稀」 という人生の節目を迎えて、今までの成果を私なりにまとめてみることとした。
私は一介の技術者であって、法律の専門家でもなければ学者でもない。
それが主に裁判の判決に関する論文を書くことになったのは、例の東京高等裁判所 (以下東京高裁という) の 「驚くべき均等論判決」 との出会いからである。
この判決については、特許の実務家の間では、ほとんどの人が反対していたが、発表される論文は 「均等論万才」 とか、「均等論元年」 とかいったシンパ的論文ばかりで、その判決の理論構成の正否について検討したものは、ほとんどなかった。
そこで特許実務家として、均等論はいかにあるべきかを念頭におきながら、その判決のどこに問題があるのかを、甲乙各号証を比較検討することによって考察した結果、このような問題の多い判決が確定してしまっては、特許の世界が混乱してしまうという危機感を持ったので 「特許侵害事件における事実認定に問題はないか」 という論文にまとめて発表した。
それは当該事件について最高裁判所 (以下最高裁という) が差し戻しの判決を出す丁度一年前 (執筆したのは一年半前) であった。
この論文発表については、陰でいろいろと批判もあったが、最高裁判判決に先行して問題点を指摘したということで、れなりに有意義であったと自画自賛している。
その最高裁判決理由の中に、均等論適用の要件についての記述があったために、この判決があの 「驚くべき均等論判決」 を東京高裁へ差し戻したものであるという前提条件を忘れて拡大解釈する論文が次々と現れて、再び暴走の気配を見せ始めた。
そこで、最高裁の説示した均等論適用の要件を私なりに展開して、均等論のあるべき姿を世に問う必要があるように思われた。
「私説均等論」 はかくして生まれた。 従ってこの論文は、あくまでも私個人の独自の解釈であって、世間一般の均等論の紹介や解説ではない。
更に、均等論適用の要件についての立証責任に関しては、格別な検討もされないまま、あたかも当然の帰着であるかの如く扱われている節があったので、その立証責任について再検討を行い、まとめたのが 「均等論適用に対する否認と抗弁に関する試論」 である。
私の知る範囲では、この立証責任の所在について、正面からとりあげた論文は他にはないと思う。
次に、本書では残念ながら論文を提示できなかったが、司法制度全搬について考えてみることとする。
司法制度については、いろいろと改革案が出されているようであるが、市民の側から見て最も重要な問題は、被害者或いはいつ被害に会うか判らない不安な市民 (以下被害者等という) の人権の保護である。
ところが一般に人権というと、不思議なことに犯人の人権のみが念頭にあるようで、被害者等の人権はいつも忘れられているように思われる。
被害者の救済についても最近よく耳にするが、被害に会ってから救済してもらっても、市民の要望を満たすものではない。 市民が求めているのは被害に会わないことである。
犯人の人権を云々する前に、まず被害者等の人権を守るというのが本質論ではないだろうか。
ところで刑事事件でいつも問題になるのが心神喪失者等の犯罪であって、ここでも今述べた人権保護の本質論の欠如を指摘しなければならない。
現在の刑法では刑事責任は問えないことになっているので裁判にもかけられないのである。
そうすると、その事件の被害者の人権はどうなるのであろうか。
刑事と民事は別であるから、民事でやれば良いと言われるかも知れないが、警察が十分な調査をやっていないものを、被害者個人で何ができるのであろうか。
結局のところ、被害者自身の行動に責任があるという事になってしまうのであろうか。
もしそうであるなら、刑事責任を問えない人物であることを表示させなければ、被害者等の人権は守られないことになる。
そしてもし犯人に対して刑事責任を問えないと判断するなら、その関係者が必要な予防処置をとったかどうか、その処置に瑕疵がなかったかどうかを必ず検討し、刑事責任を追求しなければならないと思うが、どうであろうか。
次に裁判官について付言すれば、前述の 「驚くべき均等論判決」 もそうであったらしいが、俗称卒論判決と言うものがあって、裁判官が退官する直前に、世間を騒がすような 「驚くべき判決」 を出す例があると聞く。 後述のBBSの事件では、どうであったであろうか。
退官後の弁護士としての営業環境を向上させたいという思惑であろうけれど、裁判に真理と正義を求める我々市民にとっては迷惑千万である。
退官予定1年前からは、直接判決に関与することを避け、後進の指導とか、調査官としての業務とかに専念すべきである。
これらを問題については、論文にまとめるつもりであったが、遂に果たすことができなかった。
「弁理士制度改革への提言」 は、依頼者側からみれば、必ずしも十分とは思えない弁理士の能力向上を願って、弁理士会や日本知的財産協会へ投稿したものであるが、時期的問題があって日の目を見なかったものである。
今思えば、いろいろと手を入れたいところもあるけれど、原文をそのまま入れることとした。
その他の著作、作品については、残っていた断片を収集して、私の人生の足跡としてまとめて見たので、大方の御批判を仰ぎたい。
中には、最早収集不能の資料も含まれていて、懐旧の思いも、ひとしおである。 |
|